【中学受験体験記 親子インタビュー】都立武蔵中学 合格のMさん
2025.10.31

-
東京都立武蔵高等学校 附属中学校 合格
親子インタビュー

Mさん
通っていた塾
- 学志舎
中学受験に向けた勉強を始めた時期
小学4年生
志望校に惹かれた理由
地球全体の問題を探究する武蔵中ならではの「地球学」
目次
続きを見る
※本記事は2025年7月28日におこなった取材をもとに執筆しています。
都立武蔵を目指し、「もっと知りたい、学びたい」が叶う塾へ転塾
編集部
まず、都立受検をしようと決めた理由から教えていただけますか?
Mさん
僕は理系教科が好きで、特に数学が好きなんですけど、都立武蔵は数学オリンピックの優勝者とか、すごい人が卒業しているんです。それに、理系の学習環境が整っていて、「地球学」という独自の授業があることにも惹かれて都立武蔵に入りたいと思いました。
編集部
私立中の併願は考えなかったのでしょうか? 都立武蔵1本?
Mさん
公立が嫌なわけではなくて、落ちたら公立中に行くで良いと思っていました。それなら、都立武蔵1本でちゃんと対策したいなと思って。
編集部
なるほど。5年生の時に、それまで通っていた塾から「学志舎」へ転塾したそうですが、どういった理由があったのでしょうか?
Mさん
最初に入った塾は、事前に授業動画を見た後で塾でひたすら問題演習をやるスタイルだったんです。でも、僕にはそれが合わなくて。「先生から直接授業を受けていないのに、本当に学べているんだろうか」という違和感がずっとありました。
編集部
学志舎に移って、その違和感は解消されましたか?
Mさん
はい。自分の実力に合わせて先生が追加の課題を出してくれたり、分からないところはとことん教えてくれたり。一人ひとりに合った学びができて、僕の「もっと知りたい、学びたい」という気持ちに、全力で応えてくれました。おかげで、楽しく勉強できました。
編集部
学志舎での印象的な先生や授業はありますか?
Mさん
どの先生もそうなんですが、添削コメントがすごくしっかりしていました。「良かった点」「悪かった点」だけじゃなく、「こうすればもっと良くなる」という未来に向けたアドバイスをくれるんです。それで「もっと作文を上手くなりたい」という意欲に繋がりました。
「暗記より、断然楽しかった」適性検査型入試の思考力問題
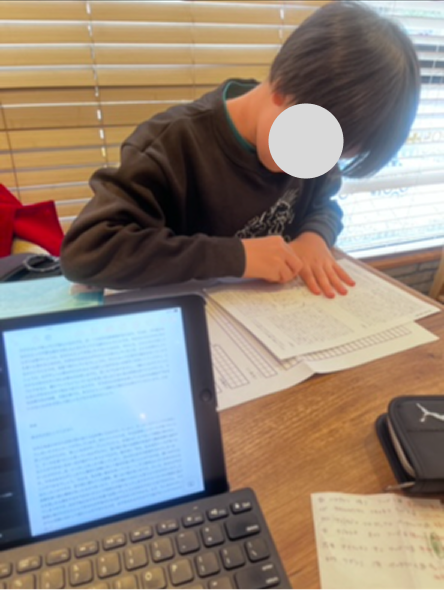
編集部
都立武蔵の適性検査は、思考力が問われる難しい試験だと思います。その辺はどうでしたか?
Mさん
そうですね。武蔵の試験は暗記じゃなくて、「知識をどう使うか」が問われます。初めて見る資料をその場で分析して記述するような問題は、書き方の練習も必要で難しかったです。でも、単に覚えるだけの暗記科目よりは、断然楽しかったです。
編集部
Mさんのお話からは「楽しい」「学びたい」という言葉が何度も出てきますね。受験勉強のどういったところが楽しかったのでしょう?
Mさん
全く知らなかった内容に出会った瞬間の、「うわー、すごいな!」っていう感覚です。学習するというより、新しい知識が自分の中に入ってくるのが面白いです。
特に算数では、全然関係ないと思っていたことが、ある瞬間にパッと繋がることがあるんです。その瞬間が、すごく気持ちよいです。
編集部
すでに数学者のようですね(笑)!
武蔵の受検に挑む上で、苦手な分野はなかったのですか?
Mさん
作文が苦手でした。でも、何度も先生とやり取りして、やり直しました。
編集部
苦手な作文を攻略するために工夫したことはありますか?
Mさん
苦手なので、やりたくないなと思うこともあったんですけど、でも最初の1行目をとにかく書いてみることを意識しました。書き始めると案外書けるんですよ。そうやって、気持ちを切り替えながら進めていきました。
編集部
合格発表の日のことは覚えていますか?
Mさん
はい。怖くて、自分でホームページ上の結果を開く勇気がなくて、発表時間に寝ていたんです(笑)。「起こさないで」って頼んで。そうしたら、母親の「うわー!」っていう叫び声で目が覚めて。「受かったよ!」って言われました。
自分がやってきたことは無駄じゃなかったんだって分かって、もう安堵と嬉しさでいっぱいになりましたね。
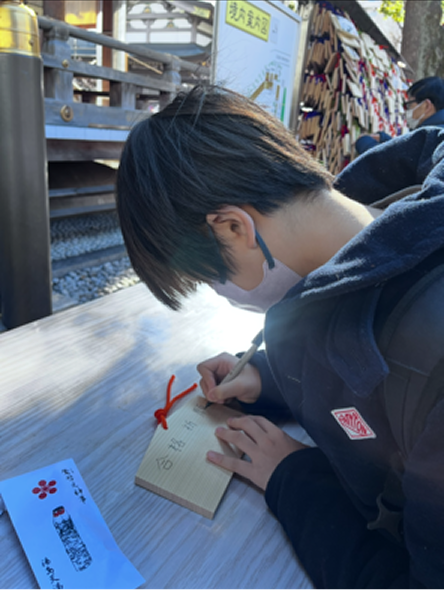
中学受験の先で得た武蔵での学び
編集部
今、憧れだった武蔵での学びはどうですか?
Mさん
すごく心地良い環境で勉強ができています。学ぶことを邪魔しようという人が誰もいないですし、その上、周りを見渡すと自分よりも頭のいい子がたくさんいるんです。
努力したら良い結果がちゃんと出るんですけど、それでも自分よりすごい成績を出している子がいて、目標をずっと高く持てるんです。充実しています。
編集部
理数系の授業はどうですか?
Mさん
想像以上です。武蔵は数学担当の先生がとても多いんです。なので、いろんな先生の解き方を学べて1つの方法に統一されていないのも面白いです。
「地球学」の授業では、ただ教科書を読むだけじゃなくて、実際にフィールドワークに出かけたり、自分でテーマを決めて研究を進めたりしています。「暗記」ではなく「どう使うか」を学ぶ授業で、受験勉強で培った考える力がそのまま繋がっている感じです。
編集部
まさにMさんが求めていた学びがあったのですね。
Mさん
はい。理科の実験でも、結果だけを覚えるんじゃなくて、「なんでこうなるんだろう?」ってみんなで考えるプロセスをすごく大事にしています。毎日が新しい発見の連続で、自分が知りたかった世界がここにあるんだと実感しています。
編集部
Mさんの将来の夢、差し支えない範囲で教えてください。
Mさん
職業としては海関係がいいなと思っていて、 漁師とか海洋研究者とか海洋生物全般に関わることができればいいなと思っています。大学も幅広く見たいなと思ってるんですけど、まあ、その関係なら海洋大学とかですかね。そういう理系の大学を考えたとき、逆算すると武蔵かなっていうので受検校を選んだので。
編集部
中学受験の先まで考えた選択だったのですね!素晴らしいですね。
家庭生活が受験だけにならないように
編集部
では、お母様にもお聞きしたいと思います。息子さんの受験を振り返って、今どんなふうなことを感じていらっしゃいますか?
Mさんのお母さん
じつは最初に入った塾から、学志舎への転塾は私が提案したんです。そこでは「ご飯・睡眠・トイレ以外は全て勉強しろ」って言われました。お稽古も全てやめるようにと。それはちょっと重いなと感じましたし、このままこの塾で過ごしたら病んでしまうなと思いました。
プライベートと塾の時間、メリハリをつけることがこの子には重要で、そういった選択があったから受験を乗り越えることができたのかなと思っています。
編集部
そうでしたか。ご家庭では、どんなサポートを心掛けていらっしゃいましたか?
Mさんのお母さん
主人は、知識を一緒に得ることが好きなんですね。「笑わない数学」っていうNHKの数学番組があって、それを一緒になって楽しんだりしていましたね。
私は、思考の幅を広げてほしくて、色々な本を読むことを勧めたりしていましたかね。勉強そのものは塾を信頼してお任せして、彼のコンディションを整えるのが私たちの役割だと考えていました。
編集部
コンディションを整える、というと?
Mさんのお母さん
受験だけではなく視野を広げてあげることと、メンタルを整えることですかね。受験を怖がりすぎない環境を作ることです。家庭生活が受験だけにならないように気をつけていました。
「受験はゴールじゃない、1つの通過点」
編集部
最後に、これから中学受験に臨む後輩たちと親御さんへ何かアドバイスがあれば!
Mさん
受験を特別なものとみないことです。他の勉強と一緒なんですよ。受験はゴールじゃなくて、1つの通過点でしかないので。
どっちかというと、僕は受験後も同じぐらい勉強してるんです。たくさん学びを得ていく上での1つの通過点として受験があるだけなんで。だから、ちゃんと息抜きもして、ここまで勉強したら休憩するみたいなことを決めておいて、進めていくといいと思います。
編集部
お母様はいかがですか?
Mさんのお母さん
本当に息子が言う通り受験はゴールではないので、たとえ残念な結果でも、すべてが終わるわけではないんです。中学受験は、親がどこまで子どもと寄り添っていけるかが問われる期間なんじゃないかなと思います。
子どもの「行きたい」が本心なのか、親の顔色をうかがってのものなのかをしっかり見てあげる。その子が本当に楽しんでいける場所を見つけてあげることが、受験が終わった後の、その先の親子関係にとって一番大切なのではないでしょうか。
取材後記
「受験は通過点。僕は受験後も同じくらい勉強しています」。
Mさんのこの言葉に本当に驚きました。彼にとって受験は、越えるべき壁ではなく、むしろ知的好奇心を加速させるイベントだったのかもしれません。
それを可能にしたのが、受験一色にならない環境を整え、息子さんの「学びの意欲」に向き合い続けたご両親の存在です。親が子どもを信じ、いつどんな時も寄り添うことの尊さが、Mさん親子の穏やかな表情から伝わってきました。
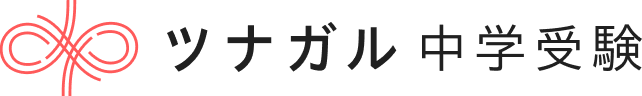


 親子
親子
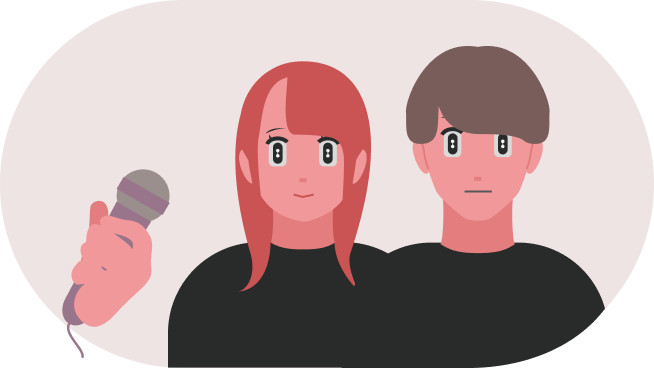 卒業生
卒業生
ぜひ感想を教えてください!