【特別インタビュー】国語の過去問どう進める?専門家に聞く採点のコツや国語の入試対策
2025.10.02
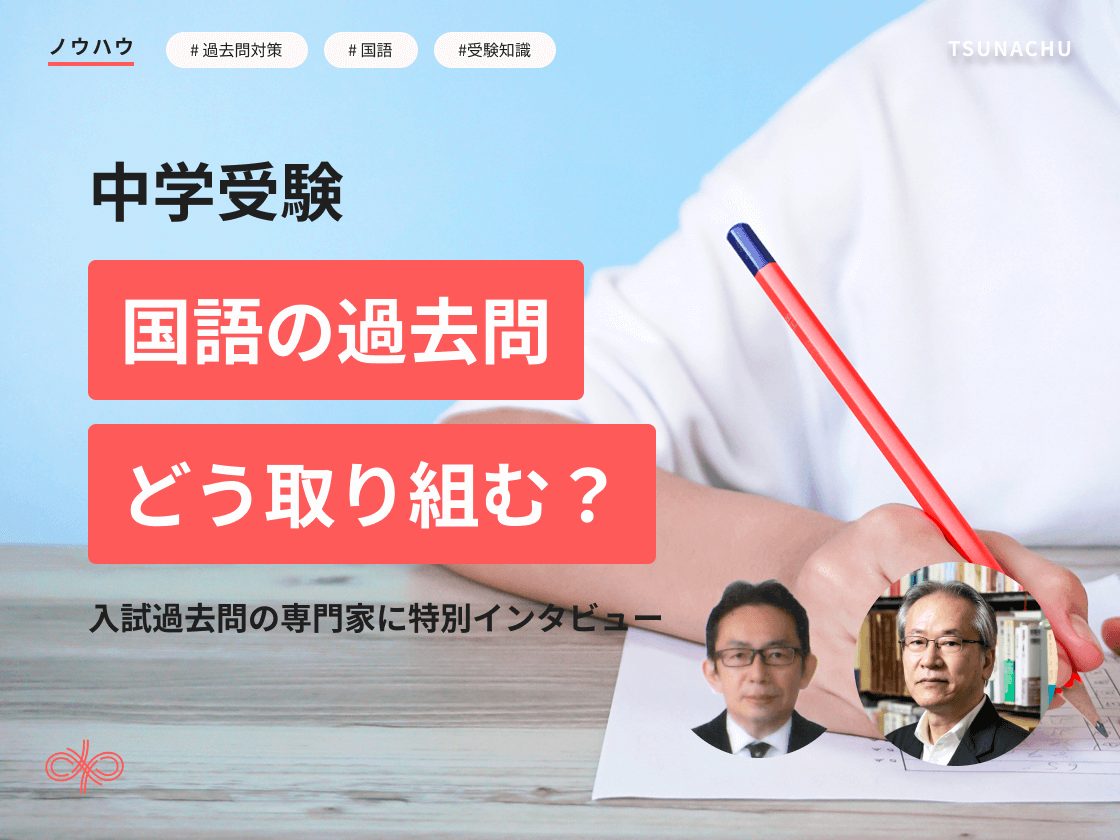
中学受験最大の山場ともいえる「過去問」。
塾で教えてもらうにも限界があるし、親の学力では歯が立たない問題もあるし、気づいたらもう時間もないし…
中でも国語の過去問については「どう教えていいかわからない」「解説を見ても答えに納得がいかない」とモヤモヤしてしまうご家庭の声をよく聞きます。
この記事では、長年にわたって入試国語を研究し著書も多数出されている、早稲田大学教授・石原千秋先生と、中学校別過去問題集を出版している「声の教育社」国語科ご担当の寺内成史さんにお話をうかがい、国語の過去問への向き合い方や国語入試の乗り越え方を解説しています。
お話を聞いた方

石原千秋さん
早稲田大学
教育・総合科学学術院 教育学部 教授
東横学園女子短期大学助教授、成城大学文芸学部教授を経て現職。 中学入試から大学入試まで、国語の入試問題についての著書、連載多数。
お話を聞いた方

寺内成史さん
声の教育社 国語科
声の教育社にて30年以上、中高国語の入試過去問編集に従事。
この記事を書いた人
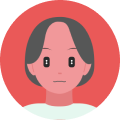
スエヨシ
目次
続きを見る
過去問が語る学校の「個性」と「教育理念」
まずおさえておきたいのは、中学入試の国語の問題は、単なる知識やテクニックを問うものではなく、学校が何を大切にし、どのような生徒を求めているかというメッセージが込められているものだということです。
課題文を選ぶときにも、設問を作成するときにも、学校の先生方は意図や想いを持って取り組まれています。
先生方からのメッセージ=学校の「個性」や「教育理念」を過去問からどのように読み解けばよいか、石原教授にお聞きしました。過去問を解き始める前の準備運動です。
女子校と男子校、問題傾向の明確な違い
はじめに、女子校と男子校の傾向の違いについてです。
女子校と男子校(特にトップ校)の入試問題には、求める思考様式に明確な違いが見られると石原教授は指摘します。
- 女子校:「情報の整理整頓問題」が多く、複雑な情報を整理して答えを導く能力を試す
- 男子校:「メタレベルに立つ思考」や「批評的読解力」が求められる
女子校は「情報の整理整頓問題」が多い傾向にあります。
複雑な情報を整理し、まとめる能力を試すもので、問題文が長く複雑でも、答え自体は比較的シンプルに設計されていることが多いそうです。
一方、男子校(特にトップ校)の評論問題は、メタレベルに立たないと読めないような問題が出題される傾向があります。
補足
「メタレベル」とは、与えられた一つの視点で読んでいくのではなく、異なる視点で論じられている内容の論点を批評的にとらえることです。
たとえば、「環境破壊を止めて地球を大事にするべき」という主張の課題文が出題されたとして、その主張に沿えば設問が解けるようになっているのなら、「メタレベルに立つ思考」は必要ありません。
しかし、課題文が「環境破壊と言われているものは破壊ではない。だから地球は大事にしなくてもいい。」という主張だった場合、それまで常識だと思っていた「地球を大事にすべき」という価値観でそのまま読んでいては、おそらく設問に答えることができないでしょう。
「そういう価値観、考え方もあるのか」と課題文を読み、設問の答えを見つけていく必要があるため、高度な思考力が求められます。
 石原教授
石原教授
学校は、受験生が「経験したことのない価値観に出会ったとき」の思考を試しています。道徳的思考が強すぎる子や、常識から抜け出せない子は、特に男子の難関校に対しては苦労すると思います。
僕は「紙の上での不良であれ」とよく言っているのですが、つまり、試験では常識だけで物事を考えなくていいよということです。「いい子」だとこういう問題に太刀打ちできないからです。
ご家庭で国語の過去問に取り組む際も、親御さんがお子さんに対して「常識ではこうだよね。でも、あえてこれを聞いているのはどうしてだと思う?」といったような声かけをする場面も出てくるでしょう。
もしかすると、これまでの子育てで「これはダメなことだよ」と教えてきたことが覆されることもあるかもしれません。
とはいえ、中学入試の国語ではそもそも「道徳的」「常識的」に考えられることが大前提です。一部のトップ校を除いては、「常識」を問われることもとても多いのです。
ですから、女子校でも男子校でも共学校でも、まずは一般的で常識的な価値観を知ることはとても重要です。
自分がどう考えるかは置いておいて、「みんなならこう考える」という思考ができるレベルを目指しましょう。
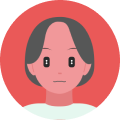 編集部
編集部
スエヨシ
中学入試国語に求められる「みんなならこう考える」「紙の上の不良」などの思考についてもっと深く知りたい場合は、石原教授の著書が大変参考になります。
また『秘伝 中学入試国語読解法』には、教授ご自身が息子さんと取り組んだ受験挑戦記も収録されています。読みごたえがあっておすすめです。ぜひ読んでみてください。
問題の「質」から見抜く学校のメッセージ

少し視点を変えてみましょう。
石原教授は、入試問題は学校の「一種の広告」であると言います。
 石原教授
石原教授
特に、記述問題にどれだけ手間をかけて採点しているかという姿勢は、学校の教育への熱意や生徒一人ひとりへの向き合い方が如実に表れます。
たとえば、麻布中や浅野中は、記述問題を出して丁寧に採点することで知られています。
これは、入学後も生徒一人ひとりに向き合い、手間をかける可能性が高いということ。先生たちの覚悟の表れですよ。
麻布中や浅野中に限らず、入試の採点は夜を徹して行われるとも聞きます。
受験生ももちろん頑張りますが、先生方も「入試」というコミュニケーションを通して、真剣に受験生と向き合っているのです。
入試は、学校が求める力を試す場でもありますが、ある意味では「私たちはこういうふうに生徒と向き合いますよ」というメッセージを出す場でもあるのです。
単に問題数が多かったり、あえて読みにくい文章でひっかけ問題を多くしたり、「ふるいにかける」問題を出す学校が存在するのも事実です。
ですが、そういった問題が得意なお子さんもいますし、良し悪しの問題ではなく「合うか合わないか」の範囲になるでしょう。
このことを理解したうえで、ご家庭で「学校のメッセージを受け取ろう」と意識するだけでも、国語の過去問への取り組み方や志望校選びがぐっと熱を帯びたものになるのではないでしょうか。

毎年、約250校もの入試過去問を出版する声の教育社には、学校の先生方からのお話も自然と集まってきます。
声の教育社の寺内さんが、入試問題に関する興味深いエピソードを教えてくださいました。
 寺内さん
寺内さん
ある女子校の先生がこんなことをおっしゃっていました。
「私たちは、試験の帰り道、あるいはもっと後になってでも、試験に出ていた作品を書店や図書館で手に取ってくれたらいいなと思って課題文を選び、試験問題を作っています。」
それだけ、先生方は受験生に豊かな作品に触れてほしいと思っているし、もっと言えば、国語の授業が入試から始まっているつもりで向き合っているということですね。
お子さんに「こんな問題をつくる先生の授業を受けてほしい」という視点から過去問を見てみると、その先に先生方の顔が見えてくる気がしませんか?
過去問を見極めるヒント:いろいろな学校の問題に触れる
とはいえ、過去問から学校のメッセージを読み解くなんて、よっぽど読解力がないと無理?と思いますよね。
たしかに、ある程度の研究が必要ではありますが、石原教授によると、まずはいろいろな学校の問題を見てみることが有効だそうです。
受験を考えていない学校の問題も含め、多くの過去問に触れることで、志望校の傾向を客観的に理解できるからです。
いろいろな学校の過去問を眺めてみて、それぞれの学校の出題方針を比べてみると、先述したような「メタレベルに立たないと解けない」問題なのか、「常識が備わっていればある程度解ける」問題なのか、ということを見極めることができます。
過去問を1校ずつ購入するのはちょっと負担かな…というときは、主要な中学校の問題が掲載されているこんな本もおすすめです。
合格を引き寄せる!今日から実践できる効果的な過去問活用術

ここからは、具体的な学習方法とご家庭のサポートについて掘り下げます。
声の教育社の寺内さんの実践的なアドバイスをメインに、石原教授の視点も交えながら、効果的な過去問活用術をご紹介します。
記述問題対策:採点基準を意識する
まずは、多くのご家庭が頭を悩ませる記述問題についてです。
過去問の解答とお子さんが書いた解答を見比べても、合っているのかどうか判断できなかったり、部分点があるのかないのかもわからなかったりします。
過去問の自己採点のときにどのように考えればよいか、寺内さんにお聞きしました。
ただし、実際の採点がどのように行われているのかはそれぞれの学校で異なりますので、1つのヒントとして参考にしてください。
- ポイント1.キーワードの特定と確認
模範解答に含まれるキーワードが自分の解答に入っているかどうかが重要です。
例えば40字の解答なら2〜3つ、60字なら3つほどをめやすに、キーワードを特定します。解説に入っている場合もありますが、まずはじっくり課題文を読んでみてください。
特定したキーワードをいくつ入れられたかで、おおよその部分点を算出しましょう。
- ポイント2.基本的な日本語表現
文章構造がしっかりしていること、誤字脱字がないこと、文末表現が適切であることも評価されます。
たとえば、理由を問われているのに、文末が「~~から。」になっていないとか、書き出しと結びの係り受けが誤っているとか、基本的な日本語が正しく書けていないのは減点対象です。
- ポイント3.「納得できない問題」を深追いしない
意外に重要なのは、たとえ納得できない解答があったとしても、過度にこだわる必要はないということです。
学校が公表する解答や過去問に記載されている解答とお子さんの書いた解答が異なっていたとしても、キーワードがきちんと入っていて、日本語的にも問題なければ「ざっくりマル」でOK。
 寺内さん
寺内さん
解答が一字一句同じかどうかにこだわり過ぎる必要はありません。課題文の内容の理解ができていればいいのです。
選択問題対策:記号だけでなく「選択肢の文言」を書く
選択問題は、記号が合っていれば安心してしまいがちですが、「どうして合っているのか」を理解することが重要です。
その確認のために、「正解の選択肢の文言を自分で書き写す」ことが有効だそうです。記号ではなくて、選択肢を書き写して解答するのです。
解き直しをする際も、なぜその選択肢が正解なのか、あるいは自分の理解のずれを明確にするために、ぜひ実践してみましょう。
また、こうした勉強は、他の記述解答の作成にも役立ちます。
 寺内さん
寺内さん
選択問題に限りませんが、できれば、おうちの方も一緒に問題を解いてください。一緒に解くことで、どうして合っているのか/間違っているのか、どこに書いてあったのか、どういう順番で考えればよかったのかを共有でき、どこでつまづいていたのかを深く理解することができます。
問題へのアプローチ:課題文ファーストで深く理解する
国語の読解問題を解く際には、シンプルですが課題文の理解が不可欠です。
 寺内さん
寺内さん
まずは課題文をしっかり読んで内容を理解することが大切です。設問から入ってはだめです。必ず課題文から始めて、解いた後も課題文に戻ってください。解答と解説は「自分の考えの方向性を確認する」という程度でOKです。
国語の問題へのアプローチについては、石原教授もこう語っています。
 石原教授
石原教授
学校の先生は、出題した課題文の内容を深く理解してもらいたいと考えています。設問はその理解度を確認するためのもの。
テクニカルな解法に頼るだけでなく、課題文の理解に努めることが、真の読解力を養ううえで不可欠です。
お子さんの様子を見て、「解答は合っているけれどいまひとつ理解していないのでは?」と感じたら、親御さんから課題文全体の内容について会話してみましょう。
「キーワード」を聞いてみたり、登場人物の変化について聞いてみたり、お互いに気づいたことを共有したり、なんでもかまいません。自分の言葉でアウトプットすることが大事です。
「繰り返し演習」が合格への鍵
過去問は、一度解いて得点を出したら終わりではありません。
同じ問題を何度も解くことで、記述問題でどのような要素を答えに含めるべきか、どのようなキーワードが求められているかの方向性がわかるようになります。
 寺内さん
寺内さん
「答えを知っているのに何回もやって意味があるのか」とよく聞かれるのですが、答えを覚えてしまっていてもいいんです。もちろん、選択肢の記号だけ覚えて答えるのはダメです。でも、「あ、この問題はこういうことを聞かれてたんだったな、だからこの選択肢でいいんだな。」となるのはOKです。
記述問題も、答えに至るプロセスや、解答に含めないといけないキーワードを確認することが実力アップにつながります。
答えを覚えてしまっていてもいいというのは意外ですね。重要なことは「できた/できない」ではなく、「なぜできたのか/なぜできなかったのか」ということです。
時間のない中ではあるでしょうが、志望度が高い学校の過去問はここまでやりきることを目指したいですね。
激変する中学入試国語の「今」を知る
ここからは、寺内さんと石原教授のお二方に、最新の中学入試国語の出題傾向や、重視されていると思われるポイントを聞きました。
形式は変わらず、内容は多様化する試験問題
 寺内さん
寺内さん
前提として、出題形式自体、つまり問題の数や、抜き出し問題と記述問題の割合など、見た目のカタチが中学入試において大きく変わることは稀です。
ただ、難度という意味では、近年は全体的に難しくなっているという印象が強いですね。
受験生は小学生なので、出題形式がガラッと変わってしまうと、それだけで点数に大きな影響を及ぼしてしまいます。そのため、形式の変更で難度が左右されることのないようになっているということです。
出題形式が変わるときは、必ず学校説明会で先生から説明がありますので、少しでも受験を検討している学校の説明会には参加しておきましょう。
前年から変更がある場合は、説明会で詳しい出題形式などが聞けるはずですので、似たような問題を出している学校の過去問で練習しておくと安心です。
難化する国語入試と「情報処理能力」の重視
 石原教授
石原教授
中学入試国語は僕も全体的に難化していると思います。具体的には「課題文の長文化」と「情報処理速度の重視」だと思います。
これは明らかに、大学入学共通テストの影響です。学校側には、中学入試の段階で共通テストに太刀打ちできる力を確認したい意図があるのでしょう。
難化の背景には、入学後に「文章が読めない」生徒が増えているという現実もあるようです。やはり、授業を円滑に進めるためには一定程度の国語力を要します。
学校は、入学後の学習や大学入試まで見通したうえで問題を作成しているということです。
入試国語課題文の最新トレンド
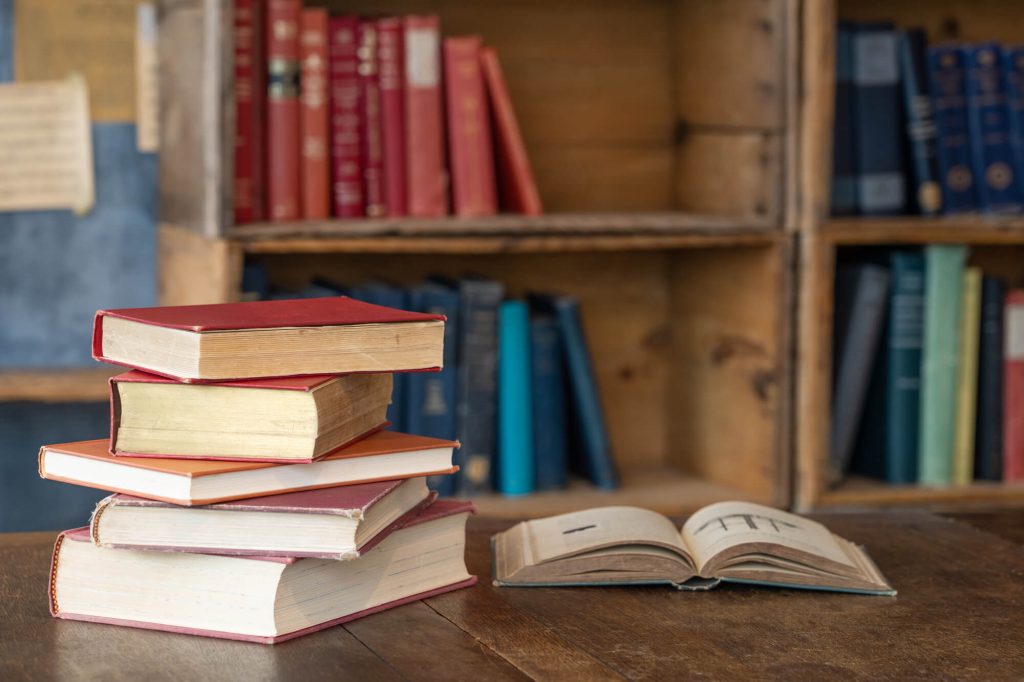
次に、課題文のテーマについてはどうでしょうか。
中学入試では、文学的文章では「物語文(小説)」、論理的文章では「説明文」が出題されることがほとんどです。
どちらかの場合もありますし、どちらも出ることもありますが、出題傾向についてはある程度トレンドがあります。
それぞれ見ていきましょう。
まずは物語文です。
 寺内さん
寺内さん
物語文は、新しい作品が出題されることが多い傾向にあります。学校は、塾で扱われる可能性のある作品をできるだけ避けたいのです。
「オチ」を知っているかどうかで解けてしまう問題がどうしても出てくるからです。
だからこそ、試験本番で「あ、この本読んだことある!」を少しでも増やすべく、可能な範囲で読書をして、試験に出そうな作品に触れておくのも良い選択です。
いわゆる「手あかがついた」作品はあまり出題されないため、その年に出版された新刊の中から目星をつけましょう。
編集部スエヨシの’26出題予想
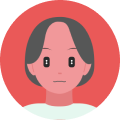 編集部
編集部
スエヨシ
おもに小中学生が主人公となる作品で、比較的新しいものを集めました。もちろん、古い作品から出題されることもありますので、志望校の過去問の傾向は確認が必要です。
次に、説明文です。
説明文のトレンドを見るポイントは「テーマ」です。
以前は自然科学系(生物系や環境系)が多かった印象ですが、最近はどうなのでしょうか。
 寺内さん
寺内さん
最近は「多様性」や「トランスジェンダー」、「自己肯定感」「自分らしさ」といった社会的テーマが増えています。
社会情勢や価値観の変化が大きいことを反映して、受験生に多様な視点を持ってほしい、自分とは異なる立場の人の価値観について考えてほしいという学校側の願いが表れていると言えます。
一時期多く見られたSDGs系はやや下火となっているようですので、もし塾や家庭学習で取り組む問題が偏っているようならば、テーマの異なる問題も取り入れるなどしたほうがよいでしょう。
中学受験のその先へ:子どもを支える親の役割

中学受験のための学習の中でも、国語は「伴走する」という要素が最も色濃く出る教科なのかもしれません。
親も子も「勉強しにくい/教えにくい」と感じる教科だからこそ、一緒に悩んで、たくさん会話が必要です。
今回、石原教授と寺内さんが口をそろえておっしゃっていたことは、家庭で質の良い会話を積み重ねることが「伴走」だということです。
親御さんがお子さんの思考プロセスに共感し、「なぜだと思う?」「どう考えた?」などの問いを重ねることで、お子さんが自分で答えを導き出す力を育んでいけるのです。
そしてそれは、目先の合格だけでなく、子どもが主体的に学び、深く考える力を育むプロセスそのものであり、かけがえのない経験となるのです。
国語が得意でなくても、ぜひお子さんと一緒に問題に取り組み、課題文について会話を深めてみてください。
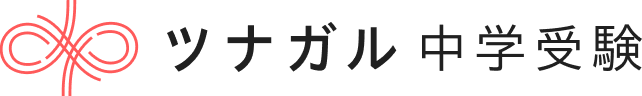


 親子
親子
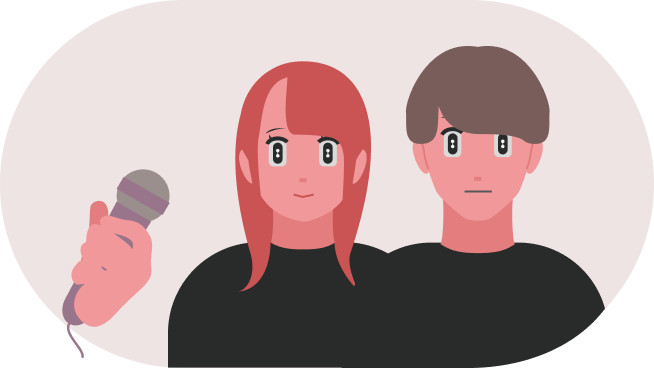 卒業生
卒業生